ベースアップ評価料 ― 2024/07/23 08:58
今回の保険の改訂で、ベースアップ評価料というものが算定できるようになった。
勤務する医療従事者の給与に回すという条件付きで一定額まで算定できるというしろもの。
これの計算がかなりややこしい。
そのうえ、算定しなければ従業員の士気にかかわりそうだし、療養の給付と関係ないのにそれがレシートで表示されて受診者は何これと思いそうだし。
給与本体に入れると年金保険料まで変わってくるのね、しかも、年金保険料は給与天引きの同額を雇用者も払うというインチキなシステムだからわけがわからなくなる。
ベースアップ評価料を算定しないとまだまだ経営に余裕があると思われるから算定しろと医師会とか医会とかからしょっちゅうメールが来る。
でもねえ、これ計算する手間って、やっぱりお金なのね。
算定する余裕もない、という方に考えてくれんかな。軽く概算して、これいちいち出す方が手間賃入れたら損や、となった医療機関は多いと思う。
医師会かなんかの説明会で、ベースアップ評価料で昇給した分は、評価料がなくなったら減給できるのかと訊いたけど無視されました、
まあできないのがわかって訊いたんですが。
財務省主導で勿体ぶってこんだけつけてやったとドヤ顔で膨大な手間を現場に押し付けて、それでどの分野もダメになってきたんだろうと思う。
by 稲亀石 [医療] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
日本代表の辞退 ― 2024/07/21 13:28
体操の日本代表19歳が喫煙飲酒で出場辞退することになった。
「社会的ペナルティーの重さに懸念」“五輪辞退”に至った宮田笙子の母校・順天堂大が声明を発表!「出場もあり得ると考えておりました」【パリ五輪】THE DIGEST
7月19日、日本体操協会は東京都内で緊急会見を開き、パリ五輪の女子代表選手である宮田笙子(順天堂大)が代表辞退に至ったと発表した。

状況としては、協会が規約で禁止している喫煙飲酒をトレーニングセンターの、人みてる前でやって人にも勧めるという状況だったそうで、お前はアホかという感じですが、、、
脇が甘すぎる、というのはまあ、そうですね。
なんか、19歳なのにその程度のことでという人と、代表なんやから当たり前やという人がいて、当たり前やの中には品格だのどうのと言い出す人がいてちょっと気持ちが悪い。
道徳律を他人に持ち出す論法は私は信用しない。
競技に関する不正でもないし、被害者がいるわけでもない。
古い話になりますが似たような感じで思い出すのは、風吹ジュンとか高部知子とか、かんなぎ中古問題とかw
イメージを込みで売るゲーノー人とは違うのに。いや、そういう路線で売るつもりだったのか?w
規約違反で違法なんだからするーするわけにはいかんでしょうが、元来自分の健康にいけないからあと1年はダメというものを不道徳な大罪のように騒ぐのが違和感あるというのです。
協会の禁止だって、法的に問題のない年齢で私生活でも禁止するならそれはおかしい。
飲酒喫煙はまず「ドラッグ」です。この視点が全面的に抜けている。
禁止されているものを、やめられないのみならず人前でへらへらやりはじめたら、依存症を考えた方がいいと思う。
依存症は「ダメ絶対」でなんとかなるもんじゃないので、成人は犯罪となるものじゃない限りは愚行権として放置するしかないけど、未成年のうちから依存症になってしまったならそれは治療対象と考えるべきであって、犯罪のように叩いたり、聖人じゃないと貶めたりしてどうするんでしょうかね。
まわりの「大人」だって知らなかったはずがないのでむしろそっちの責任問題になるのが筋じゃないですか。
急にやりはじめたのか、前からやってたならなんでここまでするに至ったのか、そういう人が代表に選ばれたのはどういう力学なのか、組織に問題は本当にないのか。
19歳はこないだから「成人」ですが、喫煙飲酒が駄目なのは「健康ガー」とやりすぎて変更の理論武装ができなかったからでしょ、だったらその部分については未成年扱いと考えるのが妥当。
世界的にはたぶん問題にならない国のほうが多いものを、どうしても問題にしたいなら、です。
こういう騒ぎをみるたびに、「他人にとにかく厳しい潔癖症社会」という、なんかどうしようもないもんを感じます。
罰があって当然とか言うけど、罰則の内容までこまかく規定されているとは見えません。
違反の程度により懲罰に軽重があるのはあたりまえです、なんぼ調子に乗ったアホ娘(すみません)でもタコ殴りにしてはいけません。
反省文と依存症治療でいいと思う。
チクりが入ったんでしょうけど、毎度代表辞退ではチクリ天国になってしまう、それはそれであとあとよくない。そういう前例になってしまいそうで嫌です。
ただ実際そのレベルで済ませて今回出場したっていい感じではもう見てもらえんでしょう。
負けたらタバコ娘とか言われて立ち上がれないくらい叩かれるだろうし、辞退で禊としてさっさと終わらせたのは本人にもむしろよかったかもしれんとも思います。
そういう社会は嫌いですが。
まー若くて先がもうちょっとあるだろうからここはさっさとひっこめたほうが傷が少ない、ということかもしれませんけどね、補充もないようなのでチームとしてもきびしいけど繰り上がって得wするもんはおらんわけで、負ける口実にもできるしw
by 稲亀石 [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
誰のための働き方改革か ― 2024/07/05 11:53
働き方改革というのは、お仕事の非属人性を高める、つまり働く側にとっては実は、「自分を替えのきく人間にする」ということですね。
自分にしかできないことがあるということで職場での地位を確固たるものにしてきたむかしの「ずっとそこにいるベテランおっさん」「どうしたらいいかまず話を通さないといけないお局」の知恵とは明らかに相反する。
それがいいか悪いかはともかく、レベルの差こそあれそういうありかたを利用してきた人も多いでしょう。
「自分の仕事」と思うことが原動力になってきた人もいるだろう。
個人の熟練度を犠牲にしても、なるべく多くの被雇用者を取り換えのきく部品にこうもあからさまにしてしまおうというのは、明らかに職場の安定のための改革なので、被雇用者側が歓迎するべきかというと、びみょーなところの筈。
一般的にこれが当たり前になったところで、私生活を犠牲にした個人の熟練度を競争力にする組織がどんと現れてもおかしくないと思う。
もともと高い属人性がいらない仕事が多いからほとんど大丈夫なのは前提ですが、「働き方改革」においての、属人性高い熟練度いる仕事の扱いがどうも曖昧なので気になる。
by 稲亀石 [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
医療機関の口コミと訴訟 ― 2024/07/02 18:40
尼崎の遠谷眼科院長先生が悪質な口コミに勝たれたそうな。
「勝手に一重まぶた」…グーグルマップの悪評削除まで3年 眼科医が挑んだ名誉回復闘争
2024/7/1 08:00 Sankei-web
「「グーグルマップ」の悪質な口コミで名誉を毀損(きそん)されたとして、眼科医院を運営する医療法人が投稿者に削除と200万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。大阪地裁は5月、請求を丸々認めたが、グーグルが投稿者の情報開示に反論したこともあり、口コミの発見から勝訴まで3年の月日を要した。「噓を噓と証明するのが、こんなにハードルが高いとは」。院長の苦闘からは、一つの口コミがはらむ〝罪深さ〟が浮かぶ。」

遠谷先生頑張られて偉いです。
大概の医者は砂を噛みながら我慢している。
「1審神戸地裁尼崎支部は「肯定も否定も率直に投稿できることが信用性を生み出しており、否定的な評価もある程度受忍すべきだ」と指摘した。」って、信用性をあるものという前提でやってる、いつもながら現実無視の地裁なんとかしてほしい。
どういう誰が何を根拠に書いてるかわからないものに信用性も何もあるかよ。
メタでは、投資詐欺に名前使われた有名人のことでこれも悶着おこっている。
プラットフォームを用意しただけという口実はもうやめたらどうか。
そこで誹謗中傷がおこって風評被害が生まれて、そのときプラットフォームに抗議したって、通り一遍の返事しか来ないんだからね。まともに対応する気がはじめからない。
「誹謗中傷のうたがいのある投稿は、IPアドレスを公開いたします」くらいな文言をはじめから載せておいたらどうなのか。
口コミが参考になるとかいう人もいますけど、「どれが本当に参考になる」かわかるのか。
まるっきりのウソを書いてあることも結構ある、うちでも息子が医院内うろうろしてることになってたり(息子はいるけど医者じゃないので医院内にはいない)。
私はもう、自院の口コミなんて一切見ない。
業者が、こんなこと書いてあります対策しますよと売り込んでくることもある、その業者がわざと書いたんじゃないかということも多い。ただのマッチポンプだ。
サクラ業者に依頼していい評価をわざと入れるのだって出鱈目は同じ。
生命に関するインフラについて匿名で口コミ流すシステムは害しかない。医者の良しあしなんて科が違えば医者にだってわからんことは多いのだ。
自分のブログだのタイムラインだのアカウントだので、誰が書いたかいざとなったら追跡できる形で感想書くのはもう仕方ないが、すくなくとも匿名の口コミのためのプラットフォームを業務として提供するのは禁止するべきです。
by 稲亀石 [医療] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
宝塚宙組公演の再開と、いじめについて思う ― 2024/06/30 16:58
宝塚歌劇・宙組 約9か月ぶり再開「待っていた きっと再生できる」多くのファン、宝塚大劇場へ
6/21(金) 2:00配信
「宝塚歌劇団の宙組(そらぐみ)公演が20日、本拠地の宝塚大劇場(兵庫県宝塚市)で約9か月ぶりに再開した。」「宙組をめぐっては、所属していた劇団員の女性(当時25歳)が昨年(2023年)9月30日に急死し、10月1日から休演中だった。」「 宙組では今年に入り、女性の同期生と下級生(後輩劇団員)の4人が退団したが、上級生を含むその他の劇団員は今回の公演に出演している」
まーあんまりわからんのですが、、
旧日本軍のようなきつい上下関係組織で上官の命令に従っただけでも、それが非人道的ということになって戦犯として処刑された人がいた。平凡な悪というやつなんでしょう。
組織の体質にひたりきっていつのまにか人間を人間として扱わなくなるのは、組織が悪いといっても、実際にそれをするのは個々の人間なんだから、自殺まで追い込んだ上級生をそのままにしておくのはどうかと思うよ。
そのままなんか知らんけど、なんかあったようには記事からは読み取れないので。
ところで、、
いじめ、は犯罪として加害者側にまず対応せんとあかんと思うが、それもともかくその「いじめ」という軽い語感の名称もなんとかしたほうがいいんじゃないですか。
ぼのぼののシマリス君の「いぢめる?」とか、

吉田戦車のいじめて君とか、

いまとなってはあのへんのネタになったのも、軽量感の理由をあらわしているような気がする、そういう扱いで世の中が「いじめ」を冗談の一部にしてしまったというか。
いがらしみきおや吉田戦車のせいじゃないですよもちろん。
by 稲亀石 [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
東アジア人の体格 ― 2024/06/04 14:51
ドイツ旅行してきた知人のいうことパート2。
日本人は体が薄いし、とくに最近は拒食症のように細いと。
まあ若いひとにそういう傾向はあるかもね、歳行ったらそんなに細くはいられない。
以下、似たようなことを繰り返し書いていますが。
ネアンデルタールの血を濃く引くコーカソイドに比べたら幼熟に進化した東アジア人がガキっぽく薄い体なのは当然なのね。
東アジア人オトコの理想進化系は童顔でマッチョなオータニサンと思っております。
生物の本能とか志向として、オスはテリトリーをなるべく広く持とうとし、メスはとにかく身の安全を優先する。
生物本来の「性欲」は哺乳類の場合「かわいいものをいじくりまわしたい」というところとつながっていて、男女ともそれは変わらない。
ただ、男について言うとテリトリーを持つためには肉体的な強さが必要になり、どうしてもいかつくなる。このへんを童顔でクリアしたオータニさんはさすがです。
女だってかわいいものがすきだから、女性にかわいいものを与えて性欲分散させてはいけない。ネコの飼育の禁止が少子化対策になるに違いないと私は思う。
で、周辺の状況が危ないとき、女は自身の安全のために、ストックホルム症候群を発揮してその場で一番強い男に発情する。
男はそれは自身のテリトリー確保と相反するのでなかなかそうはならないのだと思うが、ヨーロッパ男性に関しては、それが「豊満な女性」好みにつながるのかもしれない。
安全な社会状況で男が「守るよ」とプロポーズしても女に響かないのは当然。
男性自体が、肉体的脅威を与える一方で有用であれば女性がそちらに流れるのも、男性自身のつくりだした「危機的状況」によるもんで、悪い方にいけばDVやストーカー案件につながるもんのように思う。
安全なところで相手を威嚇する必要もなくなった(そう思ってしまった)のであれば、幼熟化で成長を拒否しする人種として拒食症まがいの痩せ方をするのも、まあ、流れとしてはありかな。
そもそも、東アジア人は子供体型なんで、ヨーロッパ特にドイツ人のペドはタイにいくというのは有名だったし(いきなり何の話w)
by 稲亀石 [日常] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
日本人の「和」 ― 2024/06/04 14:36
ドイツに行った知人が、あっちの食い物はみな味が濃い、日本の農産物は何でこうも味が薄くなったんだといっていて思ったこと。
日本人はとにかく「不快」「違和感」を除去することに執念を燃やす。
なので、日本人の好む「和」というのは反対意見のない状態であって、組織内では余計なことを言うなと言う状態に容易になる。
反論も許さないから不快なものをなくせと言う態度はカスハラに至り、客商売の口コミはあっというまに地獄化する。
農作物はきれいでひたすら甘く、あくは減り、肉はやわらかくくせもなく、漬物商品は塩素入りの水で洗われねばならず精米歩合25のコンピュータ管理されたきれいな酒が流行る。
ひたすら「違和感」を除去し不快な部分がない、ということを極めるわけです。
周辺国家に起こった、人類の文化の多様性のひとつかと思っています。
なんでこうなったとか、なおせとかいうもんじゃなく、特性なのでしょう。ドイツがいいと言ってるわけではない。あの国はあの国でこまったところはいくらでもある。
続けてみますと、、、
声のでかい少数意見におたつくくせに、なにか決めてしまったらいくら反対意見があっても無視して軌道修正しないのも、「反対意見はあってはならない」からでしょう。
「不快はあってはいけない」のですね。
だから、失敗があったら全員で懺悔するか個人の責任にしてそいつを葬り、組織は快適に温存。個人責任にしてしまうのは世界標準であることとして。全員で懺悔して終わり、というのは特に日本的と思う。
完全に、つねにそうだとは言わない。全体的にそういう傾向が目に余るということで。
考えると、「和」を乱す「不快」がいけないという文化は、「先に不快を与えたからこいつがいじめられるのは仕方ない」という発想でもあるから、いじめの対策が被害者側をいじくることに終始してしまうのだろう。
変な奴だからって、ルールを超えてそいつをいじくるなんて誰も誰にも許すことではない。
いじめの被害者が死ねば不快の原因がなくなるのだから集団としては問題が解決したことになるのがもうなんだかな。
by 稲亀石 [日常] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
日本人の「外国人嫌い」 ― 2024/05/07 14:35
バイデン大統領の、日本は外国人嫌いというのに、日本政府側が抗議した一件です。
バイデン大統領“日本は外国人嫌い”発言 日本政府「残念だ」 2024年5月4日 11時44分 NHK
「アメリカのバイデン大統領は今月1日、選挙関連のイベントで演説した際、「われわれの経済が成長している理由の1つは、移民を受け入れているからだ」と述べたあとで中国とロシア、インドと並べて「なぜ日本は問題を抱えているのか。それは彼らが外国人嫌いで移民を望んでいないからだ」と発言しました。」「日本政府関係者によりますと、この発言を受けて政府は、3日までに「日本の政策に対する正確な理解に基づかない発言があったことは残念だ」とアメリカ側に申し入れたということです。」
発言した英文がわからないので(簡単にぐぐったが情けないことに探し出せず)、ほんとうのところがよくわからんのですが、「中露と同列に置いた」「同盟国なのに」という反応はなんか違う。
「そういう文化が低調な経済の原因である」という彼なり(つかバックのシンクタンク)の分析で、ああそういうふうに見えてるんだなとまず思うところであって、なんでこうも侮辱だキーになるんかいな。
そも、日本人は身の回りを見ても報道を見てもそれなりの頻度で、異文化人との付き合い方がわからんから、とにかく危険物扱いして遠ざけることもあれば、あかんところもすべて棚に上げてしまってなんでも渡来神や無垢な被害者扱いして持ち上げることもある。
総じて、付き合い方がわからずキョドる傾向はあるだろう。
こういうのは相手を人間としてきっちり対応する(あかん外国人は蹴りだすのも含めるよ)態度ではない。一種の恐怖症(フォビア)であって、「嫌い」と称されてもおかしくないと思う。
でもねえ、日本語バリアで守られた単文化のほぼ単民族国家で長いことやってきたんだからある程度仕方ないわけで、移民でできた国に言われてもなあという気はしますけど。
(追記)
もとの用語は xenophobia だったもようで、まあ、そういうことです。
by 稲亀石 [日常] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
京都市、各区の人口構造 ― 2024/04/20 20:44
京都市東山区が出生率が日本一低いらしいw
合計特殊出生率0.76 東山区が全国最低 目立つ京都市中心部の低さ 住宅価格高騰で子育て世帯流出
4/19(金) 17:44配信 ABCニュース ABCテレビ
「厚生労働省は19日、1人の女性が生涯に生む子どもの推定人数である合計特殊出生率について、2018~2022年の市区町村別の数字を発表しました。」「全国で最も低かったのは、京都市東山区で0.76、次いで同率で大阪市浪速区と京都市上京区が0.80となりました。」「京都市下京区は0.82、京都市中京区も0.93となるなど、下位に京都市の中心部が目立っています。」「京都市では中心部の住宅価格が高騰し、子育て世帯が流出することが問題となっています。」
で、最近の京都市の統計を見てみた。出生率だけでは面白くないので高齢化率もです。
出生率
高齢化率
あくまでも大雑把、有意差あるか知らんし、血液型程度の印象ですが、、
東山区はたしかに、出生率低くて、かつ高齢化率高い。
で、上記記事の、東山区のほかに出生率の低い「中心部」なのですが、、、上京区はたしかに出生率低いが、高齢化率も低め、中京区下京区はさらに高齢化率が低い。
これはちょっと意味が違いそうに思う。
旧中京(上京区中京区下京区)つまり、むかしの京都の「まちなか」はもう家族が生涯を過ごす場所としての機能が低下しつつあるのかということなのか。働く単身が多くてもこうなる。
東山区は、働き場所もすくなく、老人が逃げ出せずに残ってる、ってことでしょうか。
そろそろ、区として扱うのはどうかという感じでないかい。
病院もまともにないしね、原田病院は七条以南、第一赤十字はさらに南で伏見区南区のすぐ際だし。眼科開業医は一軒しかないんじゃないか。
北区左京区は出生率も高齢化率も上がる。山科区右京区西京区伏見区はともに、さらにあがる。
「まちなか」から、出産家族も高齢者も山は明確に周縁に移動している。
山超えて東方面や、南方面や西方面が場所も広いだけキャパあるようですね。
左京区右京区はともにじつは北に広大な山間地域があって、高齢者はそっちからくるのかもしれんけど。
いろいろ屁理屈つけられそうで面白い。
思いつくままの出鱈目ですからね、念のため。
by 稲亀石 [社会] [京都] [コメント(0)|トラックバック(0)]
地域別保険点数構想 ― 2024/04/17 10:19
地域別保険点数とかまたいいだしたらしい。
自己負担に直結するわけです。
医師の偏在是正へ地域別報酬 財務省審議会、薬剤費抑制も提言
4/16(火) 15:27配信 共同通信
「財務省は16日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の分科会を開き、医師が都市部などに偏在している状況を是正するため、地域別の診療報酬を導入するよう主張した。医師が多い地域で診療報酬を減額するといった方法で、足りない地域への移行を促す。高齢化で増える薬剤費の抑制に向けた取り組みも進めるよう提言した。」
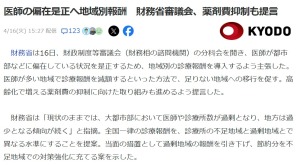
それで若手医師が田舎に集まるとか言ってる変な人もいる。もともとの住民がでていく田舎に、保険点数があがるだけで医師が集まるという思考経路は理解しがたい。
それはともかく。
前に、奈良が要望としてぶち上げたのは、うちは田舎で金がないから保険点数あたりの価格を下げろということでしたっけ、ただでさえ収入がないのによけい医者がよりつかないわと反発が出た。
今回の議論では、都市部は安くして医療側の収入減らし、非都市部(僻地とか)では高く設定して、田舎で開業しやすくしろや、僻地病院の収入もちょっとあげろやということらしい。
僻地の点数のほうが高ければ自己負担も高い。受診者側はどこにでもいける。足があれば非僻地の安い施設にいく。
現状では、全国一律どこにいっても同じ医療費で安売り競争もできない。
競争に勝つために都市部の医療を安売りする状況を、わざわざ制度でつくってどうする。
そもそも、地域を個別に管理する構想は、僻地から非僻地への交通の便をよくする名目で道路作りまくる施策と完全に相反してる。
国土の全体構想がないのがよくわかる。
さきほどの奈良でいうと、、高野原の京都側とかにびっしり開業医ができる状況が想像されておもしろい。医師会にも入らないようないわゆるチェーン店式医療機関とかその出資による開業医とかがやってきて、制度が変わって金にならなくなったらすぐ廃業するだろう。
県内受診するのは重病人ばかりになる。より高いというのがわかれば受診抑制がかかって重症化もする。ぜんぜん自治体の負担は軽減されないんじゃないか?
いろんな非対称性は、たいがいは「結果」であって、出っ張ったところだけ叩いてくねくねいじくったって全体がよくわからないゆがみ方をするだけと思うよ。
地域別に点数さわって医療費が安くなればそこから医者は逃げる、高くなれば受診者はやっぱりよそに逃げる。
役人は人間がおとなしくいわれたとおりに動くと考えていつもへんなプランを作る。ゆとり教育の失敗もそれでしょ。
道の駅の安い野菜にたまたまやってきた都会客は集まるけど、八百屋がそれで田舎にどんどんできることはない。
ところで、医療費安売り競争に関していうと、今回の改訂では、とろうとすると結構めんどうな手続きのいるへんな加算がいろいろついて、しかもそれを院内のみならず自前のウェブサイトでも公示することになった。
つまり、加算をとらない分安いよ、という売り方ができるようになってきている。
加算とらないならその分金もかからんのだし厚労省財務省は大歓迎でしょw
by 稲亀石 [医療] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
最近のコメント